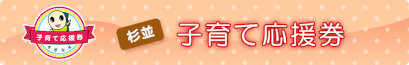切迫早産は、早産になる一歩手前の状態を指します。早産と言われると「赤ちゃんは大丈夫なのか?」、「妊婦生活どうしたらいいの?」などと不安になりますよね。
切迫早産は、適切な治療や生活習慣の改善によって防ぐことができるケースも多くあります。
この記事では、どのようなことに気を付けたらいいかなど、切迫早産について解説していきます。
目次
- ○ 切迫早産とは?
- ○ 切迫早産と早産の違いは?
- ○ 切迫早産の原因は?
- ・感染症
- ・子宮頸管無力症
- ・多胎妊娠
- ・低年齢の出産
- ・生活習慣
- ○ 切迫早産になりやすい人は?
- ・これまでの妊娠で早産や切迫早産になった
- ・子宮頸部の手術歴
- ・痩せている方や肥満の方
- ・子宮奇形
- ・糖尿病や高血圧など基礎疾患がある
- ○ 切迫早産の症状は?
- ・お腹の張りや痛み
- ・性器出血
- ・陣痛前の破水
- ○ 切迫早産の治療法
- ○ 切迫早産の赤ちゃんへの影響
- ○ 切迫早産にならないために
- ○ まとめ
切迫早産とは?
切迫早産とは、妊娠22週から36週6日までの間に、早産の兆候が現れている状態です。早産の兆候とは、子宮の収縮が頻繁に起こる、子宮頸管が短くなる、破水するなどの症状がみられる場合は、適切な治療や安静にしなければなりません。
切迫早産になったからといって必ず早産になるわけではありませんが、早産へと進行する可能性があるため、注意が必要です。
切迫早産と早産の違いは?
切迫早産は先述の通り、「早産になる可能性が高い状態」です。早産は、妊娠22週から36週6日までの間に赤ちゃんが生まれてしまうことを言います。早産は生まれた時期にもよりますが、赤ちゃんの発育が未熟なため、NICU(新生児集中治療室)での管理が必要になることが多いです。
切迫早産の原因は?
切迫早産になりうる原因は様々ですが、最も多いのは子宮内の感染症です。
しかし、感染症以外でも普段の生活習慣などが影響して切迫早産となることもあります。
感染症
妊娠中の感染症は、切迫早産の大きな原因の一つです。特に細菌性膣症(BV)、尿路感染症(膀胱炎や腎盂腎炎)、子宮内感染などが関与することが多いです。
細菌性膣症は膣内の細菌バランスが崩れることで発症し、炎症が子宮頸管に広がると子宮収縮を引き起こします。尿路感染症も発熱や炎症によって子宮が刺激され、早産につながることがあります。また、羊膜の感染が起こると、胎児に悪影響を及ぼすだけでなく、破水や子宮収縮を引き起こしやすくなります。
感染予防のためには、適切な衛生管理を心がけ、免疫力を保つためにバランスの取れた食事をすることが重要です。発熱や異常なおりもの、排尿時の痛みなどの症状がある場合は、すぐに医師に相談しましょう。
子宮頸管無力症
子宮頸管無力症とは、子宮頸管が通常よりも弱く、妊娠が進むにつれて開いてしまう状態を指します。通常、子宮頸管は出産が近づくまでしっかりと閉じていますが、この症状があると妊娠中期や後期に入る前に頸管が開いてしまい、切迫早産のリスクが高まります。
この原因には、先天的に子宮頸管が弱いこと、過去の子宮手術歴(円錐切除術や流産手術など)があります。治療法としては、子宮頸管を縫い合わせる「子宮頸管縫縮術(シロッカー手術・マクドナルド手術)」が行われることがあります。過去に切迫早産や早産を経験した人は、妊娠初期から医師に相談するようにしましょう。
多胎妊娠
双子や三つ子などの多胎妊娠は、単胎妊娠と比べて子宮への負担が大きくなるため、切迫早産のリスクが高まります。子宮が早い段階で大きくなり、子宮頸管が短縮しやすくなります。また、羊水の量が増え、子宮内圧が上昇し、収縮が起こりやすくなります。
多胎妊娠の妊婦さんは、安静に過ごし、定期的な健診を欠かさず受けることが大切です。無理な活動を避け、医師の指示に従うことで妊娠をできるだけ長く継続できるようにしましょう。
低年齢の出産
10代の妊娠・出産は、切迫早産のリスクが高いことが分かっています。これは、子宮が十分に成熟しておらず、胎児の成長に対応しきれないことがあるためです。また、10代の妊婦は栄養不足やホルモンバランスの乱れが起こりやすいことも原因の一つです。妊娠が分かったら、無理なダイエットや過労を避け、母体に負担をかけないようにしましょう。
生活習慣
妊娠中の生活習慣は、切迫早産のリスクに大きく影響します。ストレスの多い生活、長時間の立ち仕事、激しい運動、不規則な生活、無理なダイエットなどが、子宮の負担を増やし、早産のリスクを高めることがあります。
また、喫煙やアルコール摂取、カフェインの過剰摂取も、胎盤機能を低下させ、胎児の発育に影響を与える可能性があります。特に喫煙は、胎児への酸素供給を妨げ、低出生体重児や早産のリスクを高めます。
切迫早産になりやすい人は?
切迫早産は誰にでも起こる可能性がありますが、以下の条件に当てはまる人は特に注意が必要です。
これまでの妊娠で早産や切迫早産になった
過去の妊娠で早産や切迫早産を経験した人は、次の妊娠でも同じように早産になるリスクが高まります。これは、一度子宮が早く収縮しやすい状態になったり、子宮頸管が短くなったりすると、次の妊娠でも同じ現象が起こる可能性があるためです。
予防策として、妊娠初期から子宮頸管の長さを定期的にチェックし、医師と相談しながら慎重に経過を見守ることが大切です。
子宮頸部の手術歴
過去に子宮頸がんの手術や円錐切除術を受けた経験がある人は、子宮頸管が通常よりも短くなっていることがあります。そのため、妊娠中に子宮頸管がさらに短縮しやすくなり、切迫早産のリスクが高まります。
痩せている方や肥満の方
痩せすぎの人は、栄養不足やホルモンバランスの乱れによって胎児の発育に影響を与え、切迫早産を引き起こすリスクが高まります。また、BMIが18.5未満の低体重の人は、妊娠中に体重が十分に増えないことで、赤ちゃんの成長に必要な栄養が不足する可能性があるため注意が必要です。
一方で、肥満の人(BMIが30以上)も、妊娠高血圧症候群や糖尿病などの合併症を引き起こしやすく、結果として早産のリスクが高まります。適切な体重管理が切迫早産の予防につながるため、バランスの良い食事と適度な運動を心がけましょう。
子宮奇形
子宮奇形とは、先天的に子宮の形が通常とは異なる状態を指します。例えば、双角子宮(子宮が二つに分かれている)、中隔子宮(子宮内に仕切りがある)、単角子宮(片方の子宮角が未発達)などのタイプがあります。
これらの子宮奇形があると、胎児が正常に成長できるスペースが確保できず、早い段階で子宮頸管が短縮しやすくなることがあります。子宮奇形が疑われる場合は、妊娠前の段階で検査を受け、必要に応じて治療を行うことが望ましいです。
糖尿病や高血圧など基礎疾患がある
妊娠中の糖尿病(妊娠糖尿病)や高血圧は、胎盤の機能低下や血流の悪化を引き起こし、切迫早産や胎児発育不全の原因になることがあります。特に、妊娠高血圧症候群になると、子宮内の血流が悪化し、赤ちゃんの発育が遅れるリスクが高まります。
基礎疾患がある人は、妊娠前から医師と相談し、血糖値や血圧のコントロールをしっかり行うことが重要です。また、妊娠中も定期的な検査を受け、体調管理に気をつけることが求められます。
切迫早産の症状は?
切迫早産の症状は個人差がありますが、主にお腹の張りや痛み、性器出血、陣痛前の破水などがみられます。これらの症状が見られた場合は、できるだけ早く医師の診察を受けましょう。
お腹の張りや痛み
妊娠中はある程度、子宮の張りを感じることがあります。ただ、頻繁にお腹が張る、規則的に痛みがある、横になっても治らないといった場合は、切迫早産の兆候の可能性があります。
特に、1時間に何度もお腹が張ったり、生理痛のような鈍い痛みが続く場合は注意が必要です。
通常、妊娠後期には多少の張りを感じることは珍しくありませんが、強い痛みや頻繁な張りをなど違和感のある場合には、すぐに医療機関を受診しましょう。
性器出血
妊娠中の出血は、必ずしも異常を意味するわけではありませんが、切迫早産の兆候の可能性もあります。出欠の原因として、子宮頸管の炎症や感染や子宮頸管の炎症や感染が考えられます。鮮血が出る、大量の出血がある、血の塊が出るといった場合は自己判断せずに医師に相談してください。
陣痛前の破水
破水は陣痛が始まってから起こりますが、切迫早産の場合は前期破水という陣痛の前に破水してしまうことがあります。破水すると、細菌感染のリスクが高まり赤ちゃんに影響を及ぼす可能性があります。
破水の特徴として、急に温かい液体が流れ出たり、透明または黄色っぽい液体が下着にしみるといった症状があります。破水の疑いがある場合は、すぐに横になり、清潔なナプキンをあてて病院へ向かいましょう。
切迫早産の治療法
切迫早産と診断された場合は、赤ちゃんがお腹の中にいる期間が短くなるほど、生存率や予後に悪影響を及ぼす可能性が高いため、出来るだけ妊娠を継続させるための治療が行われます。
治療の方法は症状の重さや妊娠週数によって異なりますが、最も大事なことは安静にしていることです。
安静に過ごすために、重いものは持たないようにするなど、買い物や家事などは周りの人に協力してもらうなど、出来るだけ負担がかからずに無理をしないようにしましょう。
経度であれば自宅で安静にして様子を見ますが、重度の場合は入院となり子宮収縮抑制剤の投与や子宮頸管縫縮術を行います。
切迫早産の赤ちゃんへの影響
切迫早産の状態が続いて早産になってしまうと、先述の通り赤ちゃんの生存率はもちろん、生まれた後の発育に悪影響が出ることがあります。
特に、妊娠34週未満での早産では、呼吸や体温調節が未熟なため、NICU(新生児集中治療室)での管理が必要になることが多いです。
呼吸障害や抵抗力が弱まるだけでなく、脳や神経の発達の遅れなど、生まれる週数が早ければ早いほどリスクは高くなります。
切迫早産にならないために
切迫早産を予防するためには、日常生活での注意が欠かせません。
ストレスを出来るだけ溜めずに、栄養バランスの良い食事と睡眠をしっかり取るという日々の生活習慣が大切です。
産休まで働く方も多いと思いますが、重いものは持たないなど出来るだけ無理をしないようにしましょう。
また、妊婦検診は必ず受けるようにして、異常がないかを定期的に確認しておくことも安心材料の一つです。
この時期は、感染症対策やたばこの副流煙など周りの配慮も必要になりますので、家事の分担から日々の感染症対策など家族で話し合うことも切迫早産のリスクを減らすポイントです。
まとめ
切迫早産は、適切な治療や生活習慣の改善によって防ぐことができるケースも多くあります。特に、お腹の張りや出血、破水などの症状がある場合は、自己判断をせずにすぐ医療機関に相談するようにしましょう。
早産になると、赤ちゃんへのリスクも高いことを理解し、普段から無理をせず、体を大切にすることが予防につながります。
妊娠中は、自分の体と赤ちゃんを第一に考え、できるだけリラックスした環境で過ごすようにしましょう。