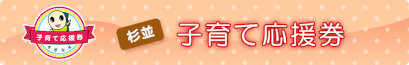逆子と診断されると、出産に対して不安や心配になりますよね。しかし、逆子が診断されても、必ずしも手術が必要となるわけではありません。
逆子の状態においては、時期や状況に応じた適切な対策を講じることで、リスクを減らし、安全な出産へとつなげることが可能です。この記事で、逆子について詳しく解説していきます。
目次
- ○ 逆子とは?
- ○ 逆子の種類
- ・単殿位
- ・複殿位
- ・足位
- ・膝位
- ・横位
- ○ なぜ逆子になるの?
- ・子宮の形態異常
- ・羊水の量
- ・胎盤の位置や幅がせまい
- ・母体の姿勢や体調
- ・遺伝的要因や多胎妊娠
- ○ 逆子にはどんなリスクがある?
- ・出産時のリスク
- ・赤ちゃんへの影響
- ○ 逆子の診断時期は?
- ○ 逆子を治すためのアプローチ
- ・外回転術(バーチャルターン)
- ・逆子体操
- ○ まとめ
逆子とは?
逆子とは、妊娠の後期において赤ちゃんが通常の位置(頭を下にした位置)でなく、逆さまに位置している状態です。
赤ちゃんはママのお腹の中で体勢を変えて過ごしていますが、妊娠週数が進む28週目ごろを過ぎると、赤ちゃんの体が大きくなり、頭が重くなります。
この時期に自然と赤ちゃんは頭を下にした状態になりますが、頭が下にならない状態でいることを一般的に逆子と言います。
逆子の種類
一言で逆子と言っても、赤ちゃんのお腹の中にいる体勢によって種類があります。それぞれの種類に応じて、出産方法やリスクが異なるため、逆子と診断された場合は、どの体勢なのかを理解しておくことが大切です。
単殿位
逆子の中でも最も一般的な形態で、赤ちゃんのおしりが下にありV字型の体勢になっている状態です。逆子の80%はこの胎位で経膣分娩も可能ですが、初産の場合は帝王切開が一般的です。
複殿位
複殿位は、赤ちゃんがお腹の中であぐらをかいた状態になっている場合です。
足が頭の大きさよりも幅が広い状態で産道を通るため、分娩の途中でひっかかったり止まってしまうリスクがあります。
足位
赤ちゃんの足が下にある状態です。足位の中でも、両足で立っている姿勢を「全足位」、片足立ちの姿勢は「不全足位」と言います。
この体勢のまま出産を迎えると、頭が最後に出る順番になってしまい、赤ちゃんが危険なため帝王切開での出産が一般的です。
膝位
膝位は足位と同じように、両膝をついた姿勢を全膝位、片膝をついた姿勢を不全膝位と呼び、この場合も頭が最後に出ることになってしまうため、帝王切開での出産になるでしょう。
横位
横位は赤ちゃんが横向きになっている状態です。肩や手が先に出てくることになり、頭が産道を通ることができません。そのため、帝王切開での出産になりますが、出産までに赤ちゃんが動くことが多く横位のまま出産を迎えるケースはほとんどありません。
なぜ逆子になるの?
逆子には、明確な原因があるわけではなく、遺伝するかどうかもわかっておりません。
ただ、逆子になりやすくなる可能性があると言われてるものをご紹介します。
子宮の形態異常
子宮に筋腫がある場合や、生まれつき子宮の形が奇形である場合は、子宮の中が狭くなっていたり、子宮の中に壁のような仕切りがあることでお腹の中で赤ちゃんの動きが制限されてしまい、逆子になりやすいと考えられています。
羊水の量
羊水が多すぎる「多羊水症」や、少なすぎる「少羊水症」の場合も、お腹の中の赤ちゃんの動きに影響を与えることがあり、結果として逆子になる可能性が高くなります。
胎盤の位置や幅がせまい
胎盤の位置も逆子の原因となる可能性があります。
通常、胎盤は子宮の上の方にありますが、子宮口を覆うように胎盤ができる「前置胎盤」や下の方につく「低置胎盤」の場合やママの骨盤の幅が狭い場合は、赤ちゃんの動きに制限がかかってしまい、逆子になる可能性が高いと言われています。
母体の姿勢や体調
母体の姿勢や体調も逆子に影響を与えることがあります。特に、妊婦さんが長時間同じ姿勢を続けることが多い場合や、特定の動きが制限される場合、赤ちゃんが自分の最適な位置を見つけられず、逆子になることがあります。また、ストレスや過度な疲労も影響を与えることがあるため、リラックスした生活や適度な運動が推奨されます。
遺伝的要因や多胎妊娠
遺伝的な要因も逆子に関連する場合があり、親や兄弟が逆子だった場合は、その影響を受けやすいと言われています。また、双子や三つ子などの多胎妊娠の場合、逆子が発生するリスクが高まります。赤ちゃん同士がママのお腹の中のスペースを取り合っているため、逆子状態になりやすくなります。
逆子にはどんなリスクがある?
逆子であることだけでは、ママや赤ちゃんの成長に影響はありませんが、逆子をきっかけとしたリスクはあるので詳しく見ていきましょう。
出産時のリスク
逆子による最も大きなリスクの一つは、出産時の難産です。逆子の状態で自然分娩を行う場合、赤ちゃんの頭が骨盤を通過するのが難しくなるため、現在ではほとんどの施設で帝王切開での出産となります。
逆子の場合は、早い時期に破水してしまう可能性があるため、早産となるリスクも高くなります。
赤ちゃんへの影響
逆子であることで成長が止まることはなく、脳の発達や身体に異常が出たりする確率が高くなる訳ではないので、ご安心ください。
ただ、逆子の状態が続くと、例えば、へその緒が赤ちゃんの首に絡まる「臍帯巻絡(さいたいかんらく)」が起こる可能性があります。これは、赤ちゃんが骨盤内で動く際に、へその緒が引っ張られることで血流が遮断され、赤ちゃんに酸素が十分に供給されなくなる状態です。
逆子の診断時期は?
逆子は、前述したように逆子と診断されてもお腹の中で赤ちゃんが動き回っているので自然と治ることが多いです。
特に妊娠初期や中期は動きが活発的な時期なので、あまり心配せずに経過を見ていきましょう。
妊娠後期の30週を過ぎたあたりになると、赤ちゃんがある程度大きくなり、お腹の中での位置が決まりつつあるため、この時期に逆子であった場合は、逆子と診断がくだることが多いです。
もちろんこの時期に診断されても逆子が確定したわけではありませんので、医師と相談して体操などこれからご紹介する改善ためのアプローチを行ってみてください。
逆子を治すためのアプローチ
逆子は赤ちゃんの成長に影響はないとは言え、流産や早産の可能性があり、できれば逆子を治したいと思う方も少なくありません、
逆子を治す方法として代表的な「逆子体操」と「外回転術」をご紹介します。ただ、これをすれば必ず治るという訳ではありません。
また、我流で行うのではなく必ず医師や助産師に相談してから行うようにしましょう。
外回転術(バーチャルターン)
外回転術は、逆子の改善方法として最も広く行われる手法です。医師が手技を使って、赤ちゃんを回転させ、頭を下に向けるようにします。
成功率は60~70%と言われていますが、帝王切開をしたことがないなどの条件があり、外回転術は、医師の技量と経験が大事なため、熟練した一部の医師しかできません。
胎児心拍の悪化を引き起こすリスクなどもあるため、慎重に判断することが必要です。
逆子体操
逆子体操は、赤ちゃんが動きやすいように促すための体操です。医学的に有効性が実証されているわけではないため、必ず逆子が治るわけではありません。
病院で逆子体操を指導された場合でも、体調の異変やお腹が張るなど違和感がある場合は、無理に続けずに安静にするようにしましょう。
まとめ
逆子は珍しいことではなく、多くの妊婦さんが経験し、自然に治ることも多いです。
逆子だからとネガティブに考えず、わからないことや心配、不安なことは医師や助産師に相談しましょう。不安な状態で過ごすことは肉体的にも精神的にもつらく、出産までに疲れ果ててしまわないように、妊娠中はリラックスして過ごすことがとても大切です。